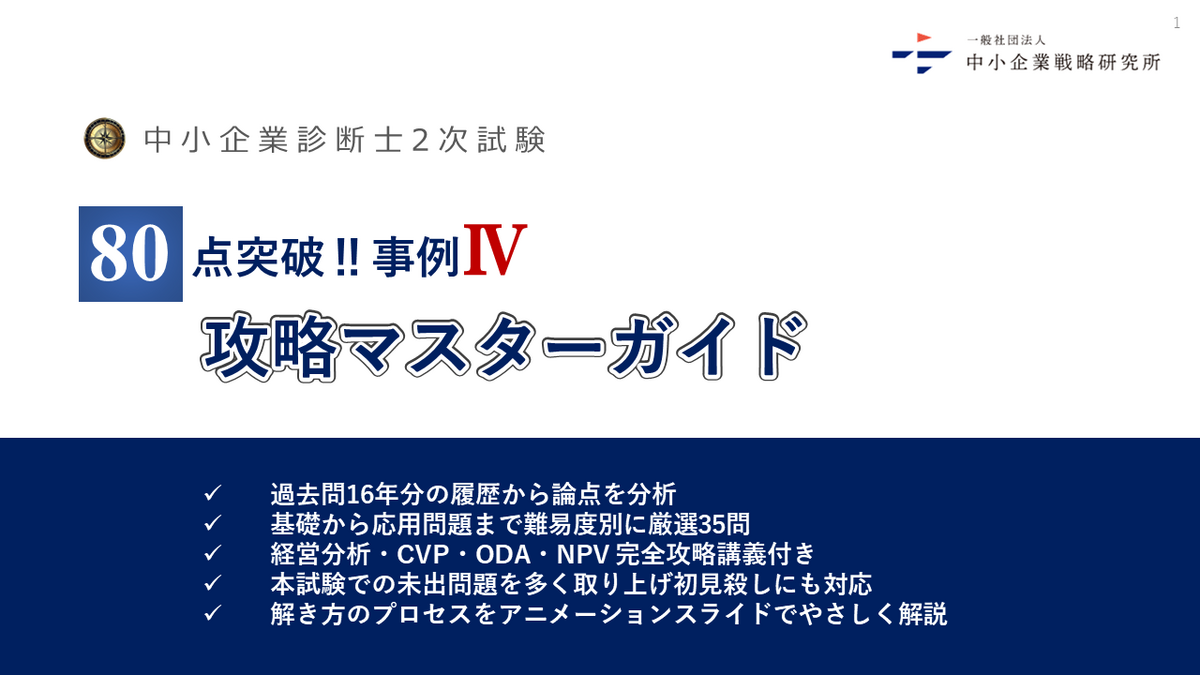こんにちは燦です。今回はまた事例ⅣのCVP分析です。
CVPとか楽勝っしょ?
そういうこという人をふるいにかけるべく、ほんの少しひねりの要素があるのはご存知ですか?
基礎がばっちりだから応用にも対応できるっしょ!
基礎編はこちら↓
中小企業診断士 二次試験の攻略⑬ 事例Ⅳ CVP分析はたった一つの式があれば全部解ける
だといいんですが…。
一応過去問から分析してみました。
1.過去問14年からCVPの論点抽出
どん!

基礎に加えて毎年ひねり要素があるね。
はい。基礎の方は例の式
売上-変動費-固定費=利益
で全部いけますよね。
不明なところをχとかにして、設問の指示通りに数字変化させてやれば問題ない。
基礎計算では変動費変化は要注意です。変動費率が変わることと売上により増減することダブルで考慮してくださいね。
H30とかはそこで間違えた人多かったみたいね。
まぁそんなのに加えて毎年スパイスがあるわけですね。
それがひねり要素です。
ふーん。いやらしいわねぇ。
てかところどころCVPが出ない年もあるんじゃね。
ですね。ちなみにCVPが出ない年は営業CFやNPVの問題ががっつり出ます。
…素直にCVPが出てほしいの。
2.過去のひねり要素をチェック
一応復習の為、それぞれチェックしていきましょう。
■H19 2期推計
2期のP/Lから変動費率と固定費を算出することが求められました。
これは変化額だけに注目すればすぐ解けます。
(当然、変動費率と固定費は2期とも同じという前提が必要)
①まず2期をプロット

※費用=売上原価+販管費
②傾きを出す(変動費率)

③切片を出す(固定費)

上のような売上費用グラフで考えてもいいし、CVPの基礎式からでも解けます。
【基礎式】売上-変動費-固定費=利益
変動費率V 固定費Fとおく
前期)3216-3216V-F=333
今期)2900-2900V-F=174
この連立方程式を解くだけ。
こっちの方が簡単では?
そうかなぁ?グラフの傾きの方が視覚化出来て好きなんだけどなぁ。
■H21 営業外損益と営業レバレッジ
金利の要素が出題されました。
本社を売却して18億円分の借金返済するというすごい話です。
金利は8%だったので1.44億円分の金利を払わなくてすみます。
元々2億円以上金利を払っていたので、この分を差し引く必要がありました。
営業外損益は経常利益の外側の話ですが、損益分析には固定費として勘定するやり方があります。
また他にも固定費を削減する案があり、それらに取り組んだ結果、営業レバレッジはどのように変化するか?と問われました。
営業レバレッジは、限界利益(営業利益+固定費)/営業利益なので、固定費(分子)が下がればレバレッジ度も下がります。
経営の安定度は増すということですね。
営業レバレッジについてはこちらでも解説しています。
■H22 グラフ線記入
珍しい問題です。損益分岐点グラフが与えられ線を引けと出題されました。
損益分岐点グラフは、実務補習でも必須なので習得しておきましょう。
基礎編の最後の方に書き方があります。↓
中小企業診断士 二次試験の攻略⑬ 事例Ⅳ CVP分析はたった一つの式があれば全部解ける
■H24 損益分岐点比率
売上3億円しかないのに損益分岐点は3.2億円ほどになり、損益分岐点比率が100%を超える状態でした。
それを90%にするには、固定費をどれほど削減すればいいかという問題でした。
まず3億円×90%で2.7億円という目標の損益分岐点売上高を出して、
2.7-2.7x変動費率-F=0 から固定費Fを求めて元の固定費と比べればOKでした。
2.7-2.7x変動費率は
2.7x限界利益率でももちろんOK!
■H27(29) PL作成
PL表を埋めてCVPをする問題で、特に難しい点はありませんでした。
PL表を埋めろという問題は、CVP以外ではH24でも出題済み。
■H28 減価償却費
新システム導入をしましたので固定費に減価償却費が加算されます。
償却方法まで書いてくれてますが、他の変化要素に気を取られつい減価償却費を忘れてしまいがちです。
絶対に忘れないようにメモしとこ。
■H29 単価計算
売電事業について総額ではなく単価で出題されました。
この場合、売上を単価×数量に分けて考えれば難しいことはありません。
百万kWhとかいう単位は聞き慣れないからわかりにくかったぞ。
■R01 部門別計算
変動費率や固定費額の異なる部門が出題されました。
全部門TOTALでは損益分岐点や各目標数字も計算可能ですが、CVP(BEP)の弱点は変動費率や固定費が変わってしまった時に精度がわけわからんくなることです。
損益分岐点分析の弱点について書けとそのまま問題となりました。
■R02 可変変動費率
これは基礎編の変動費率の変化とはまた別の話です。
売上7000万円までは変動費率65%だけど、売上7000万円を超えると変動費率が60%になるという問題でした。
実際でもありそうな話ですね。たくさん買ってくれた分についてはオマケしますよ!と仕入先に言われたんでしょう。
この場合は、7000万円でいったん区切ればいいだけです。
70(百万円)-0.65x70-固28=-3.5 (利益がまだ3.5不足している)
あとは変動費率60%(固定費0)で、不足している3.5の利益を出せばいいんです。
S-0.6S=3.5 → S=8.75
最初の70に後半の8.75を足して、78.75が答えです。
いったん区切るの発想が出来たかどうかがこの年の合格率に大きく関わっていそう…。
3.今後出題されるひねり要素を推測
試験の履歴を見てわかるように、一度出たひねり論点は基本的にもう出ません。

国家試験の特徴なのか、同じ攻撃ってあまり来ないよね。
もう出ないなら過去問を復習する意味ある??
どうなんでしょう…。一応さらにひねって攻撃してくる可能性や、混合ひねり攻撃技を繰り出してくるかもしれませんから。
今後に出題されるひねり攻撃を予測しておきたいのう。
そのとおり!同じ攻撃がこないという特徴を踏まえれば、残りの攻撃を予測することは可能!
過去問分析は過去を振り返るにあらず、未来を予測する道を示してくれるというわけか。
というわけでこんな感じでどうでしょうか。
よし、説明してくれ!
1) 勘定科目法
実務ではメインの分析法なのに、実は出題がなかったことに過去問(H19まで)を調べてて驚きました。
下表のように勘定科目を固定費、変動費に1個1個分けていくやつですね。

1科目内にも固定費と変動費の割合が混ざっているのもあります。
会社によって千差万別なので試験として出題されるならその辺は明確にされるはず。
上の表は一般的な販管費表ですが、製造原価表というのもあります。
やることは同じです。材料費は変動費、労務費は固定費ですね。
あまり細かい科目までは出ないと思いますが、簡易的な原価表からの出題はあってもおかしくはないと思います。
2) 散布図法
CVP分析の代表手法として一応あげておきますが、出題されるイメージはあまりないかも。

先程2期推計をやりましたが、そういった原価と売上のデータがもっと大量に有れば、より精密に費用線を引くことが出来ます。これも実務で使えると思います。
データをオラオラオラオラと入力してやれば上グラフのような散布図が出来ますよね。
エクセルとかだと、その点を通る直線の式も教えてくれます。便利です。
その式(傾き=変動費率(0.42)、Y軸切片=固定費(100))を使って計算すればOK。
※スキャッターグラフ法ともいいます。
3) 高低点法(最小二乗法)
これもCVP分析の代表手法。2)のやり方とかなり類似しています。
データが少なめの時に使えるかな?2)とやってることは殆ど同じですが。
こちらはCVP基礎編の最後の方で説明しています。
中小企業診断士 二次試験の攻略⑬ 事例Ⅳ CVP分析はたった一つの式があれば全部解ける
4) 可変固定費
固定費なのに可変するとはこれ如何に。
例えば…。
ケース1.間接固定費
色んな事業部があれば、自分の部門の固定費だけでなく、他の非採算部門の固定費も賄う場合があります。
3つの事業部あったとして、他の非採算部門の固定費が120だとします。

それを均等に分けるのであれば1,2,3事業部それぞれ40の間接固定費になります。
でも事業部毎におそらく規模が違うでしょうから、均等割は不公平かもしれません。

売上割合で振り分けるというのはどうでしょうか。
売上が6:3:1だとすると、関節固定費120は、72:36:12で分けると平等です。

このように、最終的な間接固定費は他の変動要素(例えば売上)によって変わるということです。
変わったとて、それを計算して数字を確定させてしまえば特に問題ありません。
ケース2.生産量で雇う人数が変わる
製品を100個まで作る時は、5人(固定費500)
製品を200個まで作る時は、7人(固定費700)
製品を300個まで作る時は、9人(固定費900)
という条件の想定は現実でもありそうです。
損益分岐点数量を計算する時には何個作るかわからないわけですから、どの固定費を使っていいかわからないわけです。
こういう時はとりあえず、えーいやぁで固定費を仮決定します。(例えば700)
それで損益分岐点数量を計算した際に、400個となったします。
そしたら固定費は900で確定されるので、改めて固定費900として再度損益分岐点を計算します。(正式には420個くらいになるかもしれません)
5) 安全余裕率
これは簡単!
問題に安全余裕率を絡めてくる可能性はあります。
安全余裕率=1-損益分岐点比率
安全余裕率=営業利益/限界利益=1/営業レバレッジ
※営業レバレッジの逆数
ということがわかっているだけで、きっと解けるはずです。
6) セールスミックス
部門別計算のひねりとちょっと似てるかも?
普通、企業は1個だけの製品を販売しているってことは少ないです。
全商品の平均的な変動費率でCVPを計算しているわけですが…。
もしA商品は変動費率10%、B商品は変動費率90%という極端な2商品を扱う企業だったとします。
となると、A:B=9:1で販売するか、5:5で販売するか、2:3で販売するかによって損益分岐点売上高が大きく変わりそうですよね。

こういうときは、「パッケージ」の発想で解けます。
つまりひとまとめのお得なSET商品のイメージです。(実際にSET商品にする必要はありません)
9:1で売る場合は、Aを9個、Bを1個でSET売りした時の限界利益を出します。
90×9 + 30×1 = 840
1SET売った場合の限界利益は840です。
なので損益分岐点SET数Nは、
840×N(SET)-5000=0
N=5.95238.... (6としましょう)
6SET売ればいいということなので、
A商品は54個、B商品は6個売ればいいということになります。
売上高でいうと、54×100+6×300=7,200
5:5で売る場合、Aを5個、Bを5個でSET売りした時の限界利益を出します。
90×5 + 30×5 = 600
1SET売った場合の限界利益は600です。
なので損益分岐点SET数Nは、
600×N(SET)-5000=0
N=8.3333.... (9としましょう)
9SET売ればいいということなので、
A商品は45個、B商品は45個売ればいいということになります。
売上高でいうと、45×100+45×300=18,000
2:3で売る場合、Aを2個、Bを3個でSET売りした時の限界利益を出します。
90×2 + 30×3 = 270
1SET売った場合の限界利益は270です。
なので損益分岐点SET数Nは、
270×N(SET)-5000=0
N=18.5185.... (19としましょう)
19SET売ればいいということなので、
A商品は38個、B商品は57個売ればいいということになります。
売上高でいうと、38×100+57×300=20,900
このように商品の販売構成で、損益分岐点売上高が変わります。
この分析方法をセールスミックスといいます。
CVP分析頑張ってくださいね!
CVP分析は割と"すこ"かも
事例Ⅳで高得点を取りたい人向けの記事
事例Ⅳ特集 ファイナル攻略マスターガイド