
こんにちは燦です。
今回、「営業レバレッジ」について触れておきます。たまーに事例Ⅳ で出てきますからね!

営業レバレッジ
営業レバレッジ?
※経営レバレッジ、オペレーティングレバレッジ等ともいいます。
要は、売上が10%増えた時に利益は何%増えるかみたいな話です。
売上が10%増えたら、利益も10%増えるのでは?
いいえそうとは限りません。仮に売上100、変動費50、固定費30としましょう。
※ここの利益とは営業利益のことです 。
おー、売上が10%増えただけなのに営業利益は25%UPしとるね。
固定費が変わらないのでこういうことが起こるんです。
この場合、売上10%UPに対して利益25%UPしたわけですから、レバレッジ具合(テコの原理)は2.5ですね。
これが営業レバレッジです。
※単位は無し(もしくは倍)
界王拳2.5倍みたいなもんじゃね。
どっちかっていうと低いほうがいいんですけどね…。
で、あくまで元の費用構造時点での営業レバレッジが2.5ですよ。
じゃあ後の費用構造での営業レバレッジは?
ではそこからさらに仮に10%売上が増えたとします。
てな感じなので、後1時点の営業レバレッジは2.2になります。
さっきの2.5より下がってるね。
固定費に対する売上が増えれば増えるほど営業レバレッジは下がります。
経営が安定化するって感じでしょうか。
じゃあ費用構造を極端な例にして考えてみようか…
例①
例②
同じ利益額だとしても、費用構造の違いで営業レバレッジは全然違うね。
そうなんです。大企業がちょっと売上落ちたらとんでもない大赤字になったりしているの見たことないですか?
あるある。
大企業ってやっぱり固定費が高いですからね。つまり営業レバレッジも高い。
仮に営業レバレッジ10だとすると、売上が10%下がると利益は100%下がっちゃいます。売上が11%下がるともう赤字ですね。
例③
変動費率の影響も受けるっぽいな。
はい、もちろん営業利益に影響を与えますからね。
例①~③を見てお気づきかもしれませんが。実はもう一つ求め方があります。
限界利益 / 営業利益 = 営業レバレッジ指数
こっちの方が変化率とか見なくていいから簡単に出せるのじゃ。
計算上はこっちの方が簡単ですね。ただレバレッジ本来の意味としては、売上が●●%増えた場合、利益がその何倍%増えるのか度合いというのを覚えておいてください。
限界利益、固定費、営業利益だけでなく、売上と利益変化率の度合いの両面から算出出来るようになっておいた方がいいね。
売上が7%増えました。
営業レバレッジが4です。
利益は何%増えましたか?
28%!!

ちなみに利益が0や赤字ならどうなるでしょうか。
限界利益/利益だから、営業レバレッジが∞やマイナスになってしまうな。
はい、売上が1%増えたら利益が∞に増える。利益0→1に増えた場合は確かに∞倍なんですが、こんな数字に意味はないですね。
またマイナスの場合も、売れば売るほど利益が減るという状態なのでそんな指数に意味はないです。
※変動費率が100%を超えていたら経済学で言う操業停止点です。営業レバレッジとか考えてる場合じゃありません。
例④
まあ確かに。営業レバレッジが△0.33であるからどうこういうより、とにかく損益分岐点の売上400まで早く持っていけって感じじゃね。
そんな経営者がいたら、「営業レバレッジ」っていいたいだけちゃうんかと問い詰めたい。
おまけ1.安全余裕率の逆数
営業レバレッジは 限界利益/営業利益 ですが、
安全余裕率は 営業利益/限界利益 です。
どちらかが分かれば、逆数にすることで求めることが出来ます。
ごっちゃにならように注意です。
普通は、限界利益(固定費+営業利益)は営業利益より多いはずなので
営業レバレッジは、分子の頭でっかち(つまり3とか4とか)
安全余裕率は、分母の足でっかち(つまり0.3とか0.5とか)
になるはずです。
そう考えれば間違えることはありません。
◆情報◆ 売上が5%増えて、利益が20%増えた。
この場合、固定費などの情報はありませんが、UP比率の方から営業レバレッジは4とわかります。(20/5)
ということは、安全余裕率は0.25になります。(5/20)
ということは、損益分岐点比率は0.75になります。(1-0.25)
上のような情報だけで色々わかっちゃうんですね。便利ですね!
おまけ2.財務レバレッジ
営業レバレッジによく似た響きで財務レバレッジというものがあります。
負債比率に近いです。(他人資本/自己資本)
自己資本の割に、どれくらい借金して経営しているかの度合いです。
株の信用取引と感覚的には同じです。
これも逆数の指数として、自己資本比率があります。
こちらの方が馴染みがあるかもしれません。
もちろん安全性という意味では他人資本が少なめで、自己資本比率は高いほうが望ましいです。
自己資本比率が高いということは財務レバレッジは低いです。
◆自己資本90 総資本100 (他人資本10)
自己資本比率 90% (安全性高)
財務レバレッジ 1.111.. (レバレッジ低)
◆自己資本10 総資本100 (他人資本90)
自己資本比率 10% (安全性低)
財務レバレッジ 10 (レバレッジ高)
ただレバレッジが高いことが常に悪というわけではなく、数字が大きいと破壊力が大きいということです。
ギャンブル性の高い経営をしているようなものですので、うまくいけば実力以上に儲かることが出来ます。
また借金が多いということは、利息の返済により経常利益を低くして節税効果を狙うことも出来ます。
資本に対する儲けの度合いを示す、つまりROAやROEとも関係が深いです。
こちらの式もついでに思い出しておきましょう。
テロア・ロアイデの式ってなんじゃ?テルマエ・ロマエみたいな。
勝手に命名した覚え式です…。
t roa roa i de でなんとなく思い出す…。
オリジナルかよ!
うるさいですね…。
こんな覚え方も
https://twitter.com/sun_smec/status/1682536295959244800?s=20
事例Ⅳで高得点を取りたい人向けの記事
事例Ⅳ特集 ファイナル攻略マスターガイド
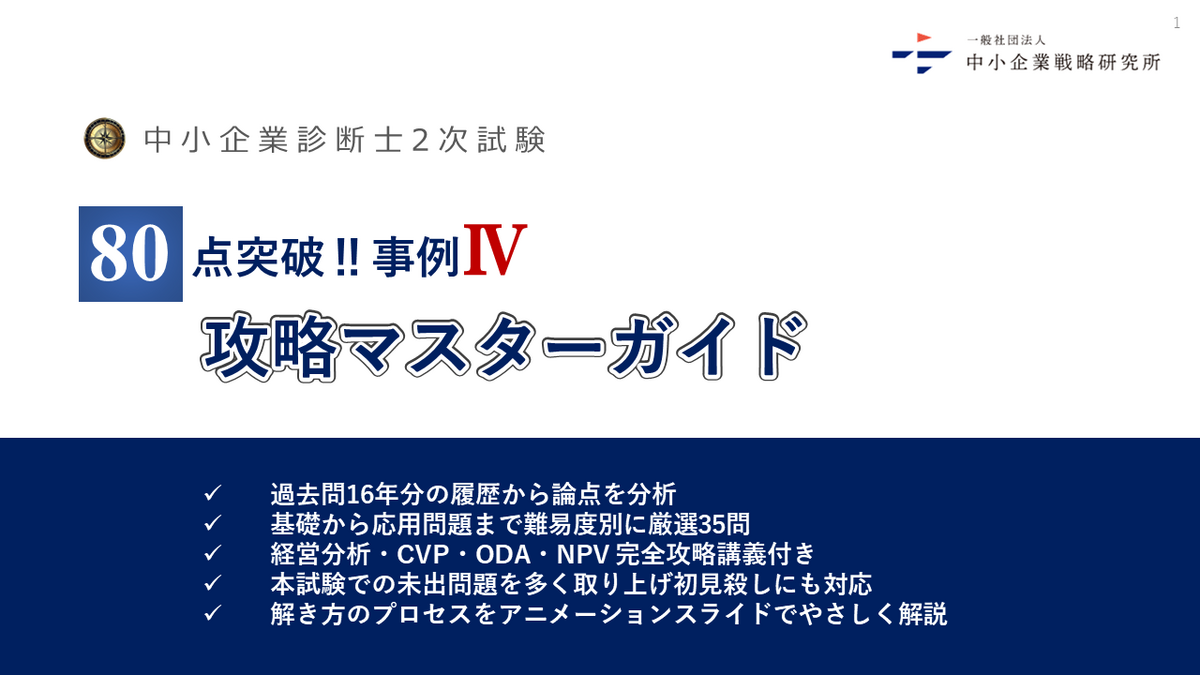
中小企業診断士講座『スタディング』のキャンペーン情報や無料お試し 中小企業診断士講座『ゼミナール』1次2次フル講座51,200円~ すごいね… ![]()
※キャンペーン割引
※3年延長無料
※質問無制限無料
※2次添削指導
※合格祝金3万円
※不合格者2万円返金